棟瓦を板金で覆う工法のご紹介1m/5000円~
この度の『大阪北部地震』と『長雨』にて依然として多くのお問合せを頂いております。速やかな御対応がなかなか適わず御迷惑をお掛け致しました事をお詫び申し上げます。
棟瓦を板金で覆う工法のご紹介 1m/5000円~
今回ご紹介する工法は上記写真の黒い筒状態の部分、『棟瓦箇所』の板金工事となります。雨漏りの原因が棟瓦に起因し尚且つ多くの予算を屋根に掛けたく無い方やまた意匠を気にされない方、今後売却の予定を見越して今は現状の雨漏りを止めたい方への御要望にお応え出来る工法となります。
こちらの工法にて2018年に上陸しました『台風21号』での飛散また今回の大阪地震での棟瓦の倒壊はありませんでした。限られた条件付きでは御座いますが選択肢の一つとして覚えて頂ければ幸いです。
工事予算は棟瓦の積み替え工事の半分位となります。因みに安全な環境で『DIY』がお好きな方でしたら御自分でも施工出来る工事の難易度となります。建材は全てお近くのホームセンターで揃います。
工事手順
①施工前
こちらは施工前の写真となります。予め予想される『不陸(屋根面の経年劣化等により発生する凹凸)』などを見ながらどの位置に後述の『杉板』を取り付けるか等の下見を致します。

②杉板の取り付け
先ずは棟瓦に沿いまして『杉板』を引いていきます。『杉板』への緊結は18cmのビスで止り付けていきます。
『棟瓦下』の『瓦屋根下地』の板が『バラ板』の場合隙間を取っている場合が殆どですのでビスが外れる事がありますがその際には打つ位置をズラシながら再度打ち直します。
また『瓦』と杉板の間に『シリコンコーキング』にて接着致しますとさらに強度が増していきます。

③雨押え板金の取り付け
『杉板』の緊結が終わりますと次に『雨押えの板金』を杉板に沿って『板金ビス』にて止め付けていきます。
細かく止めますとそれだけ強風に備えれますが瓦と瓦の感覚幅に打つだけでも十分な強度を保持してくれます。ビス一本での『耐荷重』はおよそ150㎏と言われております。

④ガルバニウム鋼板平板の取り付け
『雨押え板金』を『棟瓦』の両サイドに緊結し終わりましたら、続きまして『ガルバニウム鋼板平板』を両サイドに『板金ビス』にて緊結していきます。
その際写真の様に平板と平板との継ぎ目に『プチル両面テープ』を仕込んでおきますと更に強度と棟板金自体の防水性が増し加わります。

⑤完成!
これにて完成となりますが『瓦』と『雨押え板金』との間に空間がありますのでその空間を埋めない場合は風が入り込む場合にその風を上手く逃がさないといけません。ですから『棟板金』の両サイドは『コーキング』などで塞がない方が飛散のリスクが下がりますので2018年の台風21号では問題が発生しない実績を残させていただけました。

ありがとうございました!



を張り替えれば雨漏りは直る?-100x100.jpg)

























方法-2-100x100.jpg)
方法-2-100x100.jpg)































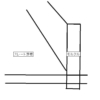



















































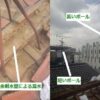















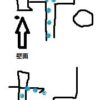
























ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません